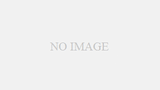実技試験については、学科試験と異なり、参考書はほとんどなく、勉強の仕方に悩んでいる受験生が多いのではないかと思います。ここでは、私の経験も踏まえながら勉強方法について紹介します。
まずは学科試験の勉強をしよう
実技試験の内容は、実技といっても、学科試験の延長線上にあります。温位や温度風といった学科一般試験の出題範囲の知識を用いて作図を行ったりします。また、衛星画像の知識や台風の構造、警報の知識といった専門試験の出題範囲についても記述問題で頻出です。1回で学科試験と実技試験の両方を突破したいと思っていても、いきなり実技試験から勉強を始めずに、まずは学科試験で10点ぐらい取れるようになってから実技試験の勉強を始めるのが良いと思います。
過去問を解こう
実技試験対策で一番重要なのは、過去問を解くことです。過去5~10年分ぐらいの過去問を繰り返し解けば十分だと思います。また、実技試験は分量が多く、時間との戦いですので、75分の時間を計りながら解くのが良いです。気象業務支援センターのHPに過去問と解答がアップロードされていますが、解説がありません。そこで本サイトでは、過去問の解答と解説を掲載していますので、ご利用ください。また、本サイトにない過去問については、「めざてんサイト」という気象予報士受験生向けのサイトに掲載されております。利用登録が必要ですが、数も多いので参考になります。筆者もめざてんを毎日のように利用していました。
過去問を繰り返し解いていくと、同じような問題が繰り返し出ていることがわかります。答え方こそ違いますが、同じ現象について問われている問題が頻繁に出てくることがわかるはずです。例えば台風であれば、温帯低気圧化したときにどのような特徴を持つのかを背景にした問題、発達する低気圧や衰退する低気圧はどのような特徴を持つのかを背景にした問題、じょう乱の移動速度を求める問題などです。論述問題の学習時には、出題者がどういう背景でこの問題を出しているのかを考えると良いでしょう。
暗記物についても、過去問を解きながら、どのような知識を問われるかを知りましょう。例えば、天気記号、予報用語(時間帯や降水の強さ、台風)、海上警報の基準などは、実技のテクニックとは別に必要な暗記知識です。暗記物は他の受験生も間違えないように勉強してくるので、間違えると合格が遠のきます。
また、作図に関してもパターン化されており、前線の解析、エマグラム、シアーライン、等圧線の補助線などの作図問題を繰り返し解いて、できるようにする必要があります。
簡単な問題を間違えないようにしよう
実技試験においては、難しい問題もありますが、穴埋めなどの簡単な問題もあります。簡単な問題を前問正解するだけで40~50点ぐらいとれます。一方で論述問題などは、部分点しかもらえないことも多いと考えられ、点数が安定しません。問題は下記の3つに分類できると思います。
・間違えられない問題(穴埋め、グラフを読み取るだけの問題、移動速度などの計算問題)
これらについては1問も間違えないつもりで解いてください。ケアレスミスも痛いですが、わからないのであれば勉強不足ですので、しっかりと勉強してください。
・できるだけ点を取りたい問題(繰り返し出る論述、単純な作図)
論述問題についても、発達する低気圧の特徴を問う問題などは繰り返し出題されており、しっかりと勉強している受験生であれば、論述問題あっても満点を狙える問題です。簡単な問題はみんな間違えないので差がつきませんが、このような問題の正誤で点数に差がついていきます。作図についても、等温線を追記する問題や、エマグラムの問題など、難しい判断が不要な記述問題も解けるようにしましょう。ただこれらの問題は合格者でも間違えることもあるので、全部できなくても合格は可能です。
・捨てても良い難問(出題頻度が少ない論述、難しい作図)
論述問題において、指定字数が多いにも関わらず、何を答えればいいのかわからないような難問が1題か2題出題されます。そのような問題は他の受験生もほとんど満点をとることはできないので、部分点を狙って何か書いてください。このような問題ではほとんど差がつきませんので、あまり勉強の優先度は低いと思います。また、難しい前線解析やトラフ解析についても同様です。
気象庁HPを見よう
学科試験も同様のことが言えますが、気象庁HPには、気象衛星画像やアメダス、天気図など様々な情報があります。日頃から自分なりに気象現象がどのような要因で起きたのかを気象庁HPのコンテンツから探って見るようにしましょう。さらにキキクルについては、実技試験で出題される災害や警報に関する知識問題において有用ですので、日頃から見ておき、知識をつけておきましょう。